今年の春から、家計簿はMoney Forwardでつけています。
つけているといっても、自分で入力するところは現金の収支だけ。
あとは銀行口座の入出金も、カードでの支払いも、すべて自動で数字を取り込んでくれ、勝手に集計してくれるので、以前のようにわざわざ「家計簿をつける」という作業をすることもなくなり、時間の節約にもなっています。
そんな自動の家計簿も、内容を整理し見直してみました。
1週間晩ごはん献立まとめ
11月13日・・・夫出張で不在。

11月14日 ビビンバ丼
![]() ☆簡単ビビンバ☆ by ☆栄養士のれしぴ☆
☆簡単ビビンバ☆ by ☆栄養士のれしぴ☆
冷ややっこ
牡蠣のレンジ蒸し
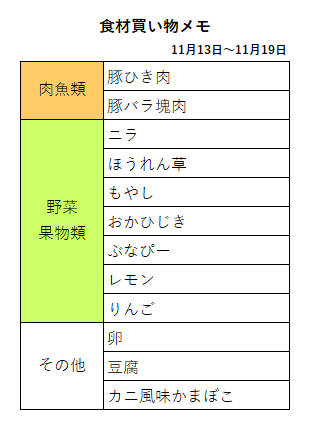 いただいたもの:牡蠣・大根・りんご
いただいたもの:牡蠣・大根・りんご

11月15日 牡蠣フライ
![]() おばぁちゃん直伝!簡単&絶品カキフライ by 槙かおる
おばぁちゃん直伝!簡単&絶品カキフライ by 槙かおる
![]() ☆3色野菜のナムル☆ by ☆栄養士のれしぴ☆
☆3色野菜のナムル☆ by ☆栄養士のれしぴ☆
牡蠣のレンジ蒸し
ワカメと大根の味噌汁

11月16日 牡蠣ごはん
![]() 身がプリプリのカキ飯 by arare*
身がプリプリのカキ飯 by arare*
わかめと油揚げの味噌汁
豆腐かまぼこ
トマトと玉ねぎのサラダ
焼き鳥(市販品)
11月17日・・・夕食各自

11月18日 豚バラの角煮
![]() 簡単!圧力鍋でトロトロ♪豚の角煮 by まこりんとペン子
簡単!圧力鍋でトロトロ♪豚の角煮 by まこりんとペン子
卵焼き大根おろしのせ
牡蠣ご飯
長芋の千切り
大根の漬物

11月19日 豚バラ大根角煮
豚バラ大根角煮
おかひじきと人参のナムル
ぶなぴーと大根おろし
長ネギとミョウガとワカメの味噌汁
家計簿を整理する
Money Forwardが自動で家計簿をつけてくれるので、すっかりおまかせしていましたが、今一度整理してみました。
たまに項目が違うところに集計されていたりするのと、自分でもわかりやすいように、項目分けをしっかりしようと思ったからです。
例えば、子どもに荷物を送った場合、家計簿の項目は「通信費・宅配便」に振り分けていたのですが、これを「子ども費」のくくりにしました。
子どもがいることでかかる費用を、すべて子ども費の枠に入れることにしたのです。
大学生の子どもの携帯電話料金も、通信費ではなく子ども費へ。
とにかく、子どもがいることでかかる費用を、全部丸ごと子ども費へ含めることにしました。
すると、今月の子ども費は44万円。
ああ、数字を見ただけでも怖ろしい。
大学生2人分の仕送りに加え、次男の大学後期の授業料の支払いがありましたからね。
今月末には、娘の大学授業料の引き落としがあるので、来月の子ども費も40万円は軽く超えるでしょう。
もちろん、授業料などのまとまったお金は貯金から払うので、毎月の生活費の中でやりくりする上では目に触れないお金・・・というか、怖くて見ていなかったお金なんですよね。
しかし、子ども費としてきっちり集計することで、見えてくるものがあります。
それは、子どもが独立したら、夫婦2人の生活費はどれくらいになるかということ。
今、子どもにかかっているお金を除いた分が、夫婦2人の生活に必要なお金であり、これが年金生活へスムーズに移行するための準備ともいえます。
老後の不安を心配するよりも、今できることは、収支をきっちり把握し、今からシミュレーションしておくことなんです。
年金生活になったら、1年間の支出額を予想し、毎月平均的な額を積み立てて暮らしていくのが、一番ストレスなくできる方法かと思っています。


コメント
はじめまして!いつも楽しく拝見させて頂いております。
母がね、軽度〜の認知障害なんです。多分そらはなさんのお母様と同じ感じなんです。
両親のこと、介護が原因で、ますます険悪になってしまった姉のことが、寝ても覚めても頭から離れません。
その不安が私の生活の全て、というか。
そらはなさんは、ご自分の生活や趣味も充実されているご様子で羨ましいです。
もちろん不安な時、おありだと思いますが、どのように乗り越えていらっしゃいますか?気持ちの切り替え方というか…..
そらはなさんの旅行の時は、お母様はどうしてらっしゃるのですか?
はじめましてなのに、すいません、質問ばかり(*´-`)
あっこさんへ♪
はじめまして(#^^#)
あっこさんのお母様も軽度の認知障害とのこと。
たぶん、この始まりの時期が家族にとって一番大変かもしれません。なんせ対応に慣れていないから。
本来であれば、兄弟姉妹で力を合わせて親の介護問題に取り組むところ、険悪になってしまったのでは、本当に不安で心配ですね。
でも、介護って家族が直接やるべきものではないと、今だから思います。
家族は、親が介護サービスを受けられるためにあれこれ準備をすること。
そして生活に必要なものを整えてあげること。
一番大事なのは「割り切る」ことなんだと思います。
幸い、うちの母はまだ自分の身の回りのことは自分で行えているので、今は私も出かけられます。
1泊程度であれば、母一人でも留守番はできます。ふだんも、私が仕事に行っている間は一人なわけですしね。
もちろん不安もありますし、今後は今より大変になっていくかと思います。
だからこそ、今できることを楽しんでおこうと思っています。
母が「怒りのスイッチ」が入る時も、この2年間で学習したので、今はそのスイッチを押さないよう気を付けていますよ!(^^)!